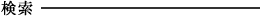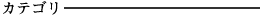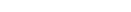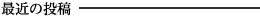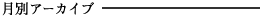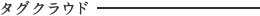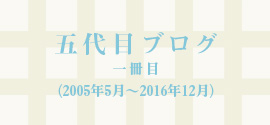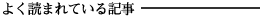バランスを取りながら/麹塵染の御召
織物を織る場合、経糸と緯糸が必要です。
となみ織物が作る織物の場合、その糸質自体は同レベル絹糸であることがほとんです。
ただ、緯糸の場合、通すのは多種の糸になることもあります。
たとえば、ベースは通常の糸でも色が違ったり、紬糸だったり、御召緯や箔を入れたりと、
様々です。
もちろん、これは自分がイメージする織物の風合いを作るためです。
糸の太さを変えるだけで、仕上がりの光沢も変わりますし、
微妙な中間色を作るため、違う色を絵の具の様に混ぜて色を表現することも。
これらは、試験をしながらバランスを取って進めていきます。
今日のモノづくりは、緯糸に麹塵染の糸を入れて、御召を織る。
そんな仕事です。
ちなみに、帯と着物の糸は、太さや合わせ方など点が微妙に異なります。
もちろん、使えないことはないのですが、帯の糸は帯の表現に特化した糸ですので、
それで着物を織ったり(以前は帯締めを組む)する際には織に難いことが、多々あります(苦笑)。
それでも、
じぶんがイメージするモノにするため、どうしても使わなくてはいけない場合もあります。
その際は、なんとかお願いしますが、着物としての形に到達しないこともありますので、
こちらもバランスを見てのモノづくりになります。
崩しすぎても駄目ですし、従来通りの定石通りでは、面白くない。
この麹塵染めの糸を使った『仙福屋の御召』づくりも何度目かになりますので、
今までとは少し変えて、一歩踏み出たモノづくりに仕上がる予定です。
-

2024年1月30日 21:00
奄美にいます今日まで奄美にいます。 いつも通り目的はモノづくりですが、… -

2024年1月25日 21:00
松皮染・帯/2柄目染色中『松皮染・帯/2柄目染色中』 今週のはじめに撮らせて頂きまし… -

2024年1月23日 21:00
総紗縫・改をはじめてみる。久々に連続でブログを更新しています。職人さんは減り、新しい… -

2024年1月22日 21:00
南蛮七宝文様の有線ビロード・輪奈着物の生地としては本当に少なくなりました。 業界全体として…
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (8)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (2)
- 2023年8月 (4)
- 2023年7月 (3)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (5)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (6)
- 2022年12月 (5)
- 2022年11月 (3)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (3)
- 2022年8月 (3)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (3)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (7)
- 2022年3月 (8)
- 2022年2月 (3)
- 2022年1月 (4)
- 2021年12月 (5)
- 2021年11月 (7)
- 2021年10月 (8)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (6)
- 2021年6月 (13)
- 2021年5月 (5)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (7)
- 2021年2月 (6)
- 2021年1月 (7)
- 2020年12月 (5)
- 2020年11月 (11)
- 2020年10月 (7)
- 2020年9月 (7)
- 2020年8月 (6)
- 2020年7月 (4)
- 2020年6月 (5)
- 2020年5月 (4)
- 2020年4月 (6)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (7)
- 2019年12月 (8)
- 2019年11月 (8)
- 2019年10月 (6)
- 2019年9月 (9)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (10)
- 2019年6月 (6)
- 2019年5月 (7)
- 2019年4月 (9)
- 2019年3月 (7)
- 2019年2月 (7)
- 2019年1月 (9)
- 2018年12月 (10)
- 2018年11月 (11)
- 2018年10月 (11)
- 2018年9月 (9)
- 2018年8月 (9)
- 2018年7月 (7)
- 2018年6月 (8)
- 2018年5月 (10)
- 2018年4月 (11)
- 2018年3月 (11)
- 2018年2月 (13)
- 2018年1月 (12)
- 2017年12月 (14)
- 2017年11月 (17)
- 2017年10月 (15)
- 2017年9月 (22)
- 2017年8月 (24)
- 2017年7月 (27)
- 2017年6月 (25)
- 2017年5月 (29)
- 2017年4月 (9)
- 2017年3月 (11)
- 2017年2月 (10)
- 2017年1月 (13)