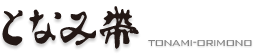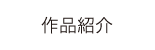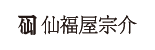2011年7月の記事一覧
2011/07/25
■蜻蛉(とんぼ)

今回は、古くから私達の身近に在り続けている『蜻蛉(とんぼ)』についてのお話です。
この『蜻蛉』、実は非常に歴史ある昆虫だったんです。
『蜻蛉』の先祖は、およそ3 億万年以上前に棲息していた昆虫といわれ、現在生息しているものは古代の昆虫の生き残りともされています。
古く日本は『秋津島(あきつしま)』と呼ばれていました。この『秋津』とは、当時『秋津(アキツ、アキヅ)』と呼ばれ親しまれてきた『蜻蛉』を指しています。
これは日本神話に登場する神武天皇が国土を一望して「蜻蛉のようだ」と言ったことからとされ、「蜻蛉島(あきずしま)」ともいわれました。
また、平安時代には生命の儚い姿が陽炎に例えられ『蜻蛉(かげろう)』ともよばれました。

現在の『蜻蛉(トンボ)』という名前でよばれるようになったのは、鎌倉時代の頃です。
なぜそう呼ばれるようになったのかは定かではありません。ですが羽根を広げ飛んでいる姿が、穂が飛んでいる光景を思わせ、「飛ぶ穂」が「トンボ」となった。また、「飛ぶ棒」が「トンボ」になったなどといわれています。いずれにしても、「トンボ」は庶民に親しみやすいよび名として、広く定着していきました。
そして、この蜻蛉が最も好まれたのが戦国時代。
前にしか進まず退かないという性質から、強い虫をあらわす「勝虫」や「勝軍虫」とも言われ、蜻蛉の文様は縁起物として武士に好まれ武具や着物の文様として用いられました。
また、勝負と同音の菖蒲に蜻蛉が組み合わされた文様や、矢に蜻蛉が組み合わされた文様は、とくに縁起がよいものとされたようです。
蜻蛉は、夏から秋にかけて稲穂につく害虫を食べることから、「五穀豊穣」の意味もあります。

江戸時代になると、蜻蛉は縁起の良い文様としてだけではなく、水辺の風情をあらわすものとしても着物や帯の意匠に用いられるようになりました。
2011/07/22
■立湧(たちわき)
平安時代より、公家の装束・調度・御輿車(みこしぐるま)などの装飾に用いられた独自
の様式をもつ文様を総称して有職文様(ゆうそくもんよう)と呼ばれています。
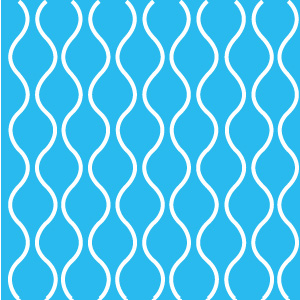
今回ご紹介する縦に均一に揺らめく文様も代表的な有職
文様のひとつで、『立涌文(たてわくもん)』または『立枠文
(たちわきもん)』ともいわれています。
この『立湧』という名称は、二本の曲線を雲気、水蒸気が
涌き立ちのぼっていく様に見立てた事から名付けられ、古くから縁起のよい吉祥柄
として親しまれてきました。

立涌は形の上では幾何学的文様ですが、そのふく
らみの中に、図案化した雲・波・藤・菊・松などを入
れることで、「雲立涌」「波立涌」「藤立涌」「菊立涌」
「松立涌」と立涌の中にもさまざまな文様が生まれ
ました。
このような多彩さを発揮した幾何学紋様は他に例が
無く、幾何学紋様としても特異的な存在です。立涌
は向かい合う波状型の線の繰り返しが、不思議な律動を生み出し、「静」と「動」を不断
に調和する魅力をもっています。そのため静物に施された場合でも、少しの光の当たり
方や見る角度によってゆかしくその動きを醸し出します。
一方、装束に施された場合、わずかな仕草を見事なリズムに変えてゆきます。また、
その大きさや密度を変えることによっても受ける印象は大きく変わってきます。能
装束などに立涌が好まれて利用されたのも、このような魅力によるようです。
この文様は平安時代の織物に多く見られる伝統的な文様ですが、実際には奈良
時代に中国から伝えられたものといわれており、 近世も非常に格調高い文様として
江戸小紋や西陣織・袖織物に多用されています。柔らかでリズムのある上品な文様
なので光沢のある織物の見た目を引き締める効果もあり、帯地の地紋に使われる
ことも多いです。
2011/07/22
■鯉(こい)
 昔から立身出世を招くとされ多くの人々に親しまれてきた、鯉文様。
昔から立身出世を招くとされ多くの人々に親しまれてきた、鯉文様。
着物の柄として描かれるのはもちろんですが、お皿などの陶磁器にも多く見られ、私達の生活に非常になじみのある柄だと言えます。
最近では洋服やジーンズ、帽子なんかにも描かれることが多くなってきましたね。
ですがなぜこんなにもこの文様が愛され続けたのでしょう?
それはやはり、先人達が託した鯉の意味にあります。
中国の黄河という川の上流に竜門という急な滝があり、ここを越えられた魚は龍となって天に昇る事が出来るという中国の故事があり、この竜門を多くの魚の内「鯉」だけが昇り切って龍となる事が出来たので、鯉は出世魚として立身出世を表すとされました。
5/5の端午の節句に鯉幟を揚げて男の子の健やかな成長を願ったり、才能が世の中に認められる最初の関門を“登竜門”というのも、このような理由からだといわれています。
昇進栄達・立身出世 鯉の滝登りの図案
江戸時代以降、吉祥文様として親しまれた鯉文様は、特に男の子の着物の文様として「鯉の滝のぼり」の柄が好んで描かれてきました。
しっかり、出世して立派な大人になってほしいという親心の現れですね。

名物裂と呼ばれるものの中にある荒磯文様
名物裂とは、今より600年程前の鎌倉時代から江戸時代にかけて、貿易品として主に中国から日本に伝わってきた最高級の織物の事です。これは現在確認されている物のうちの一つで、波の間に踊る鯉を描いた最もポピュラーな文様です。荒磯というのは、本来岩の多い荒波の打ち寄せる海辺を意味しますが、この柄では、跳ね上がった鯉の姿から、荒波を想像して荒磯文様と呼ばれています。
となみ自慢の鯉は、迫力満点な伊藤若冲の鯉図です。

2011/07/22
■伊藤若冲の世界より「砂糖鳥」

こちらは伊藤若冲の絵をモチーフにした帯です。
作品名は「サトウチョウ」。
佐藤さんの鳥????
──ではなく、漢字で書くと「砂糖鳥」。
東南アジアにすむ小型のインコの仲間で、大きさ14センチほど。
ハトよりずっと小さい鳥です。
とても鮮やかな鳥で緑をベースに青や赤、黄色の斑紋が入っています。
特に頭のてっぺんの青はこの鳥の英語名「Blue-crowned Hanging Parrot」にも現れています。
なぜ、「砂糖」鳥なのかというと、この鳥が非常に甘党だからだそうです。
虫や種なども食べるらしいのですが、なにより果物が大好き、とのこと。
さらに面白いのは、この鳥、コウモリのように枝から逆さまにぶら下がるのが大好きなのだとか。

昼間休むときはもちろん、夜寝るときにも逆さになっているそうです。
これが英語名の残り半分「Hanging Parrot」の部分。
実物は、Googleで画像検索した結果をどうぞ。
若冲はこのサトウチョウをはじめ、多くの外来産の鳥の絵を残しています。

左はオウム、右はインコ
若冲はなぜこんなにも多くの動物画を描いたのでしょうか?
それは、若冲の生きた江戸中期~後期にかけて日本で一大ペットブームが起きたからだそうです。
安定した世相を背景に、金魚や鯉などの魚類を筆頭に、さまざまな生き物がペットとして飼われるようになりました。
もちろん、サトウチョウをはじめとしたエキゾチックな鳥たちも大人気。
「南総里見八犬伝」を記した滝沢馬琴も、自分の飼っている鳥の話を日記に書いていたそうです。
そんなブームにあって、鶏をはじめ花鳥を描くのが得意であった若冲が借り出されないわけがありません。おそらく、豪商を中心としたこれらの鳥の飼い主たちが、自分の鳥を描かせたのではないかと思われます。
飼い主の愛情の伝わる作品ですね。
お江戸のペットブームについてはこんな本もありますので、興味がある方はどうぞ!