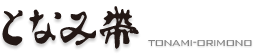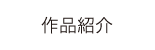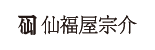2011/07/22
■鯉(こい)
 昔から立身出世を招くとされ多くの人々に親しまれてきた、鯉文様。
昔から立身出世を招くとされ多くの人々に親しまれてきた、鯉文様。
着物の柄として描かれるのはもちろんですが、お皿などの陶磁器にも多く見られ、私達の生活に非常になじみのある柄だと言えます。
最近では洋服やジーンズ、帽子なんかにも描かれることが多くなってきましたね。
ですがなぜこんなにもこの文様が愛され続けたのでしょう?
それはやはり、先人達が託した鯉の意味にあります。
中国の黄河という川の上流に竜門という急な滝があり、ここを越えられた魚は龍となって天に昇る事が出来るという中国の故事があり、この竜門を多くの魚の内「鯉」だけが昇り切って龍となる事が出来たので、鯉は出世魚として立身出世を表すとされました。
5/5の端午の節句に鯉幟を揚げて男の子の健やかな成長を願ったり、才能が世の中に認められる最初の関門を“登竜門”というのも、このような理由からだといわれています。
昇進栄達・立身出世 鯉の滝登りの図案
江戸時代以降、吉祥文様として親しまれた鯉文様は、特に男の子の着物の文様として「鯉の滝のぼり」の柄が好んで描かれてきました。
しっかり、出世して立派な大人になってほしいという親心の現れですね。

名物裂と呼ばれるものの中にある荒磯文様
名物裂とは、今より600年程前の鎌倉時代から江戸時代にかけて、貿易品として主に中国から日本に伝わってきた最高級の織物の事です。これは現在確認されている物のうちの一つで、波の間に踊る鯉を描いた最もポピュラーな文様です。荒磯というのは、本来岩の多い荒波の打ち寄せる海辺を意味しますが、この柄では、跳ね上がった鯉の姿から、荒波を想像して荒磯文様と呼ばれています。
となみ自慢の鯉は、迫力満点な伊藤若冲の鯉図です。