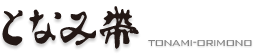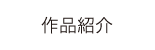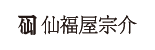2011/07/22
■立湧(たちわき)
平安時代より、公家の装束・調度・御輿車(みこしぐるま)などの装飾に用いられた独自
の様式をもつ文様を総称して有職文様(ゆうそくもんよう)と呼ばれています。
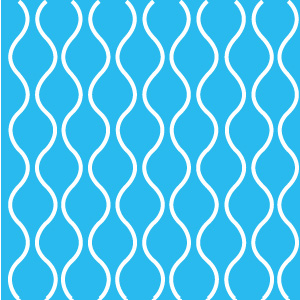
今回ご紹介する縦に均一に揺らめく文様も代表的な有職
文様のひとつで、『立涌文(たてわくもん)』または『立枠文
(たちわきもん)』ともいわれています。
この『立湧』という名称は、二本の曲線を雲気、水蒸気が
涌き立ちのぼっていく様に見立てた事から名付けられ、古くから縁起のよい吉祥柄
として親しまれてきました。

立涌は形の上では幾何学的文様ですが、そのふく
らみの中に、図案化した雲・波・藤・菊・松などを入
れることで、「雲立涌」「波立涌」「藤立涌」「菊立涌」
「松立涌」と立涌の中にもさまざまな文様が生まれ
ました。
このような多彩さを発揮した幾何学紋様は他に例が
無く、幾何学紋様としても特異的な存在です。立涌
は向かい合う波状型の線の繰り返しが、不思議な律動を生み出し、「静」と「動」を不断
に調和する魅力をもっています。そのため静物に施された場合でも、少しの光の当たり
方や見る角度によってゆかしくその動きを醸し出します。
一方、装束に施された場合、わずかな仕草を見事なリズムに変えてゆきます。また、
その大きさや密度を変えることによっても受ける印象は大きく変わってきます。能
装束などに立涌が好まれて利用されたのも、このような魅力によるようです。
この文様は平安時代の織物に多く見られる伝統的な文様ですが、実際には奈良
時代に中国から伝えられたものといわれており、 近世も非常に格調高い文様として
江戸小紋や西陣織・袖織物に多用されています。柔らかでリズムのある上品な文様
なので光沢のある織物の見た目を引き締める効果もあり、帯地の地紋に使われる
ことも多いです。