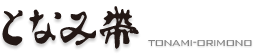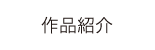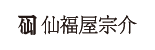2011/07/25
■蜻蛉(とんぼ)

今回は、古くから私達の身近に在り続けている『蜻蛉(とんぼ)』についてのお話です。
この『蜻蛉』、実は非常に歴史ある昆虫だったんです。
『蜻蛉』の先祖は、およそ3 億万年以上前に棲息していた昆虫といわれ、現在生息しているものは古代の昆虫の生き残りともされています。
古く日本は『秋津島(あきつしま)』と呼ばれていました。この『秋津』とは、当時『秋津(アキツ、アキヅ)』と呼ばれ親しまれてきた『蜻蛉』を指しています。
これは日本神話に登場する神武天皇が国土を一望して「蜻蛉のようだ」と言ったことからとされ、「蜻蛉島(あきずしま)」ともいわれました。
また、平安時代には生命の儚い姿が陽炎に例えられ『蜻蛉(かげろう)』ともよばれました。

現在の『蜻蛉(トンボ)』という名前でよばれるようになったのは、鎌倉時代の頃です。
なぜそう呼ばれるようになったのかは定かではありません。ですが羽根を広げ飛んでいる姿が、穂が飛んでいる光景を思わせ、「飛ぶ穂」が「トンボ」となった。また、「飛ぶ棒」が「トンボ」になったなどといわれています。いずれにしても、「トンボ」は庶民に親しみやすいよび名として、広く定着していきました。
そして、この蜻蛉が最も好まれたのが戦国時代。
前にしか進まず退かないという性質から、強い虫をあらわす「勝虫」や「勝軍虫」とも言われ、蜻蛉の文様は縁起物として武士に好まれ武具や着物の文様として用いられました。
また、勝負と同音の菖蒲に蜻蛉が組み合わされた文様や、矢に蜻蛉が組み合わされた文様は、とくに縁起がよいものとされたようです。
蜻蛉は、夏から秋にかけて稲穂につく害虫を食べることから、「五穀豊穣」の意味もあります。

江戸時代になると、蜻蛉は縁起の良い文様としてだけではなく、水辺の風情をあらわすものとしても着物や帯の意匠に用いられるようになりました。