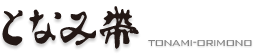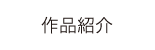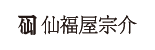2012/01/18
■源氏香(げんじこう)

源氏香とはそもそも、香道で行われる。組香の一種です。
香道とは、文字通り香りを楽しむ事を基本とした芸道で、一定の作法に基づいて香木をたき、その香
りを鑑賞して楽しむという茶道や華道と同じく、動作の中に精神的な落ち着きを求める日本古来の
伝統芸能の一つです。
今から約1400年前の推古天皇の時代に、1本の香木が日本に初めて淡路島に漂着しました。
その後、仏教の伝来と共に香木は日本に伝わり、仏教儀式には欠かせないものとして、香木は発達
しました。8世紀頃には上流階級の貴族の間で、自分の部屋や衣服、頭髪などに香をたきこめる
風習が生まれ、やがて室町時代の華やかな東山文化の下で一定の作法やルールが作られ、香道
として完成しました。そして江戸時代に入り、貴族だけのものではなく、一般の町民・庶民の間にも
広まり、香道は日本の伝統芸術として確立したといわれています
その、香道で行われるのが組香です。
組香は、数種類の香りを組み合わせて香りを聞き(嗅ぎ)分けるという風雅な遊びです。
この組香では、和歌や古典文学を主題にして、香りを組みます。
そして主題の中で最も人気の高い主題が源氏物語を主題にした組香「源氏香」なのです。
まず、5種類の香木をそれぞれ5包ずつ(合計25包)用意します。
この25包を交ぜ、その中から5包を選び、それぞれを香炉入れて順にまわし、香を聞きます。
香炉が5回まわり、すべての香が終了した後、
その香を紙の上に右から順に縦の棒線を引いて表し、同じ香のもの同士は横線で繋ぎます。
この時使われるのが、香の図とも呼ばれる『源氏物語』52帖にちなんで付けられた符号です。
この符号は52通りあり、それぞれに『源氏物語』最初の「桐壷」と最後の
「夢の浮橋」を除いた52帖の名称が付いています。

源氏香文様は、その幾何学的な形に優雅な物語性が備
わった文様として愛好され、源氏物語の巻名やその内容
に関係する草花や器物を添えたり、図の中に小柄を詰め
たりして表すこともあります。
現在でも晴れ着や帯から浴衣まで、幅広く用いられて
います。

帯 『光源氏の世界』

帯 『光源氏の世界』
帯締め 光沢帯締め 濃いピンク
帯揚げ 白地にしぼり梅の帯揚げ