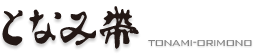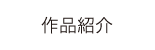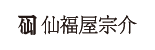2011/08/26
■兎(うさぎ)

まだまだ暑い日が続いていますがお盆を過ぎると日が落ちるのも徐々に速くなり、もう
すぐ秋が来る気配を感じます。そんな時にふっと「あぁ、もうすぐ十五夜だな」っと思うん
です。
そこで今回は十五夜には欠かせない兎の文様についてです。
そもそもなぜ、月に兎がいるという話が伝わっているかと言うと、大昔インドから伝わっ
た伝説が元になっています。

昔、猿・狐・兎の3匹が、力尽きて
倒れている老人に出逢いました。
3匹は老人を助けようと考え、猿
は木の実を集め、狐は川から魚
を捕り、それぞれ老人に食料とし
て与えました。
しかし兎だけは、どんなに苦労しても何も採ってくることができませんでした。
自分の非力さを嘆いた兎は、老人を助けたいと考えた挙句、自らの身を食料
として捧げるべく火の中へ飛び込んだのです。その姿を見た老人は、帝釈天
としての正体を現し、兎の捨て身の慈悲行を後世まで伝えるため黒ごけにな
った姿を月の中に納めたので、月には兎のシルエットが残されたという。

この話は仏教に取り入れられ、飛鳥時代
の頃中国を経て日本へ伝えられました。
そして経由した中国からも兎が不老長寿
の霊薬を作るという伝承が伝えられたた
め、正倉院に伝わる当時の織物の中に
は兎が織り込まれた意匠もあります。
また、当時の人たちが満月の事を「望月(もちつき)」と呼んだ事から、発音の似た
「餅つき」を連想するようになり月でお餅をつく、お茶目な兎の姿が定着していった
ようです。
その後も、兎は月の兎だけでなく「鳥獣戯画」や「因幡の白兎」のようなキャラクター
としてや江戸時代に大流行した文様「波兎」など実に様々な形で描かれ続け、現在
も多くの方々に愛されています。

そんな、今が旬の兎を使った帯留
がWebショップ「仙福屋」で来週か
ら販売されます。月を仰ぎ見る兎の
姿が非常に可愛らしいですよ。