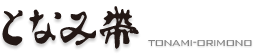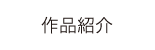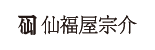2011/08/03
■撫子(なでしこ)
 最近大輪の花を咲かせ日本を元気にしてくれた日本女子サッカーの「ナデシコJAPAN」
最近大輪の花を咲かせ日本を元気にしてくれた日本女子サッカーの「ナデシコJAPAN」
今回はそのチーム名の由来となった「撫子」についてのお話です。
撫子は、花びらの先が細かく切れ込んだ淡紅の可憐な花を咲かせます。
その様子は少女がにこやかに微笑む姿に例えられ、撫でるように可愛いがっている子
= 「撫でし子」と表された事からこの名前が付きました。
また撫子は、女郎花(おみなえし)・尾花(おばな)・桔梗(ききょう)・藤袴(ふじばかま)・
葛(くず)・萩(はぎ)と、万葉集の中で山上憶良が秋の七草に選んだことから、秋の花
というイメージもありますが、秋の涼やかさを先取りしようと、むしろ夏の時期に用いら
れることが多い文様です。
また、初夏から秋と比較的長く咲く花で、「常夏(トコナツ)」という異名も持っています。
さて皆さんは、撫子は大きく分けて二つの種類があるのをご存知ですか?


一つは平安時代、中国からもたら
された「石竹(せきちく)」と呼ば
れるもの、やはり渡来ものなので
「唐撫子(からなでしこ)」と呼ば
れていたようです。


もう一つは日本に古来より自生す
る「河原撫子」「大和撫子」
と呼ばれるものです。
この二つの違いは、花びらの先の溝の深さ。浅いものは「石竹」深いものは
「大和撫子」と見分けるのだそうです。
文様的にはあまり大きな違いはないのですが、知っておくと撫子を見るとき一段と興
味を持てるのではないでしょうか?
小さく可憐で踏まれても起き上がることのできる強さを持った撫子。
日本女性の象徴とされたこの花に負けない女性になれるよう日々頑張っていきたいで
すね。